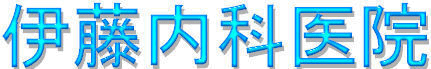活性型ビタミンDの危険性・・・エルデカルシトール投与時の定期血液検査の遵守に関して
日本臨床内科会誌 2025年3月号より引用
永井 幸広先生(石川県)
最近、エルデカルシトール0.75μg/日投与によると思われる高カルシウム血症と急激な腎機能増悪を来した患者を経験した。患者は84歳、女性で、基礎疾患として高血圧症、2型糖尿病、甲状腺機能低下症を有していた。Xー3年4月から骨粗しょう症に対してエルデカルシトール0.75μg/日投与が開始された。開始当初の腎機能はeGFRで54ml/min/1.73㎡、投与後のeGFRは30台~40台後半ml/1.73㎡を推移していた。X年4月2日の定期受診時には、特に自覚症状はみられなかったが、血液検検査上、血清クレアチニン2.01mg/dl, eGFR: 19ml/min/1.73㎡。カルシウム:10.6mg/dl. IP 4.4mg/dl. Alb: 4.2g/dlと急激な腎機能の増悪と高カルシウム血症が認められた。受診前には特に感染症、脱水を来す病態はみられず、非ステロイド解熱鎮痛剤やサプリメントの内服は行っていなかった。急激な腎機能増悪を来したためA病院腎臓専門医に紹介した。基礎疾患として腎硬化症が疑われ、エルデカルシトール投与によると思われる高カルシウム血症の関与を考慮し、直ちに同剤を中止し輸液を行ったが、腎機能は軽度の改善しかみられなかった。
2020年10月に医薬品医療機能総合機構(PMDA)から医薬品適正使用に関して「エルデカルシトールによる高カルシウム血症と血液検査の遵守について」が報告された。血清カルシウム値の定期的な検査の実施すなわち本剤投与中は血清カルシウム値を定期的(3-6か月に1回程度)に測定すること。腎機能障害・悪性腫瘍・原発性副甲状腺機能亢進症の合併やカルシウム製剤の併用時・投与初期には頻回に血清カルシウム値を測定することが強調されている。また、、高カルシウム血症の症状(倦怠感・嘔気・口渇感・食欲減退・意識レベルの低下等)が出たらすぐに受診するよう、患者やその家族へ指導する旨が記載されている。中外製薬による集計結果では2015-2019年における本剤の高カルシウム血症関連の発現件数が徐々に増加しており、かつ血清カルシウム値が定期的に測定されていなかった例数も増加傾向で2019年では12例あった。PMDAは定期的な血液検査を実施せずに高カルシウム血症が生じた症例などは、医薬品副作用被害救済制度においても適正な使用とは認められず、救済の支給対象にならない場合があると述べている。
2023年1月1日~2023年12月31日に当クリニックで本剤を投与した69例中、高カルシウム血症を呈したものは本例を含め4例であり、すべて無症状で、本剤の中止または減量を実施した。全69例中、定期血液検査が実施されていない者は約半数にみられた。糖尿病や慢性腎臓病などを併発している場合は、定期血液検査を実施しているが、高血圧症単独併発例や骨粗しょう症単独例では、なかなか定期血液検査の実施に結びついていない現状が判明した。今後はPMDAの指摘にもあるように、患者の不利益にならないためにも、本剤の内服者に定期血液検査を実施しているか慎重にチェックする耐性の構築が必要である。
コメント:そもそも、この薬を使う必要がないのではないか。(加えて0.75μは多すぎると思う。)
先日、腎盂腎炎の時に意識低下を来した患者さんがおられた。活性型ビタミンDの影響ではないかと思う。