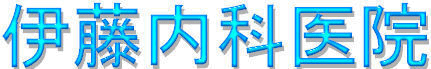αーGI再評価される。
江部先生の記事より引用
∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪
糖尿病・ダイエットに! ドクター江部の糖質オフ!健康ライフ
∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪
こんにちは。ドクター江部です。
今日の内容
■ 食後高血糖を防ぐα-ク゛ルコシタ゛ーセ゛阻害薬の役割と糖質制限食
■ 事務局からのお知らせ
・大阪講演会、交流会開催のお知らせ
♪∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪∽♪∝♪∞♪
今回は、α(アルファ)−グルコシターゼ阻害薬薬(α-GI薬)について考えてみます。
糖質制限食を実践していても、旅行や外食などで、どうしても糖質摂取せざるを得ないこともあります。
その様なときは、α(アルファ)−グルコシターゼ阻害薬薬の出番です。
デンプンのような多糖類は、α-アミラーゼという消化酵素の作用を得て、二糖類(麦芽糖や蔗糖)やオリゴ糖に分解されます。
つまり、α-アミラーゼは、穀物や芋のデンプンと呼ばれる多くの糖の集合体を、まず第一段階で分解して少し大きさを小さくしています。
その後、この二糖類やオリゴ糖は、マルターゼ、スクラーゼ、グルコアミラーゼなどの酵素により、単糖(ブドウ糖、果糖、ガラクトース等)に分解されて小腸から体内に吸収されます。
マルターゼ、スクラーゼ、グルコアミラーゼなどの酵素を総称して、α−グルコシダーゼと呼びます。
この、α−グルコシダーゼの働きを阻害することにより、腸管からの糖質の分解・吸収を遅延させて、食後高血糖を抑制するお薬が、『α−グルコシダーゼ阻害薬』(グルコバイ、ベイスン、セイブルなど)です。
グルコバイ(アカルボース)はα−グルコシダーゼだけではなく、α-アミラーゼに対する阻害作用ももっています。
ベイスン(ボグリボース)やセイブル(ミグリトール)は、α−グルコシダーゼの活性を阻害しますが、α-アミラーゼには影響を与えません。
従って、グルコバイの方が少し効果が強いですが、副作用もやや生じやすいです。
副作用とは、ガス、腹満、腹痛、軟便などです。
それぞれ常用量で下記程度に血糖値を下げるとされています。
グルコバイ: 1時間値50mg、 2時間値40mg
ベイスン: 1時間値40mg、 2時間値30mg
セイブル: 1時間値60mg、 2時間値20mg
しかし、これほど下がらない人もあります。
セイブルは1時間値を下げるけれど、2時間値はあまり下げないのが特徴です。
いずれの薬も結構個人差が大きいですし、印象としては上記の数字ほど下がらない人のほうが多いようです。
作用機序から考えて、膵臓のβ細胞には全く影響を与えないので、SU剤のように疲れた膵臓を鞭打つといった欠点はありません。
しかし、比較的頻度の多い副作用として、分解が遅れて腸管に残った糖質が醗酵してガスがでたり、お腹が張ったり、下痢をすることがあります。
ガスの貯留により、腸閉塞(イレウス)のような症状になる事があるので、腹部手術歴の有る方は、禁忌とされています。
私自身で行った人体実験では、かなり興味深いことがありました。
グルコバイの常用量を食直前に服用して何種類かの食品を試食してみました。
蕎麦はほとんど腹満がなかったのですが、お餅は最悪で、腹満・腹痛・ガスのフルコースで、病院に行こうか?と思ったくらいでした。
うどんやご飯は、蕎麦に比べたらやや腹満・ガスなど出やすかったですね。
個人差はあると思いますが、参考にしていただければと思います。
現在は、私は、食事の工夫(スーパー糖質制限食)をしていますので、内服薬は一切なしです。
52歳の時に糖尿病発症し、HbA1Cが6.7%でした。
即、スーパー糖質制限食を実践し、一ヶ月後には、HbA1c 5.9%と改善しました。
以来、75歳現在まで足かけ25年、内服薬なしで、HbA1cは5.6-5.9%です。
糖尿人でスーパー 糖質制限食実践中の患者さんの場合は、ほとんど薬はなしですが、お昼だけ主食ありの『スタンダード 糖質制限食』の時は、α-GI薬を食直前に内服してもらうことがあります。
「糖尿病には糖質制限食」の高雄病院でも比較的使用頻度の高いのが『α−グルコシダーゼ阻害薬』です。
高雄病院入院中にグルコバイ100mgを、食時開始30秒前に内服して、昼食に例えば炊いたご飯100gなどで実験し、食後2時間血糖値値が180mgを超えない量をリサーチすることもあります。
炊いたご飯お茶碗一杯は約150gで、糖質を55g含んでいますが、それでは糖質が多すぎて太刀打ちできないので、約100gに減らして実験します。
グルコバイ・ベイスン・セイブルを飲み忘れた場合、食べ始めてからすぐに飲んでもそれなりに有効です。
食事終了時に内服しても無効です。
基本的に安全性の高い薬ですが、まれに肝障害を来す例があるので、定期的な血液検査を推奨します。
朗報として、最近のCGM(Continuous Glucose Monitoring:持続ブドウ糖測定)システムの普及で、α-GI薬が、食後高血糖と共に平均血糖変動幅増大をある程度コントロールしていることが判明し、その有効性が見直されています。
2002年、2003年に、LancetやJAMA(米国医師会雑誌)に掲載されたSTOP-NIDDMという臨床試験(*)(**)で、アカルボース(α-グルコシダーゼ阻害薬・グルコバイ)による治療は、2型糖尿病の発症を36%、心血管疾患の発症を49%抑制すると報告されました。
2008年6月にヘルシンキで「第5回糖尿病とその合併症予防に関する世界会議」(WCPD)が開催され、STOP-NIDDM試験のまとめが発表されました。
あまりにも、結果が良すぎるので、当時私は信用していなかったのですが、近年のCGMの普及により、STOP-NIDDMの結果は、信頼できるものであったと納得がいきました。
CGMの普及により、α-GI薬のように見直される薬剤もあれば、SU剤のように欠点がもろに暴露された廃れた薬剤もあり、栄枯盛衰ですね。
(*)
Lancet. 2002 Jun 15;359(9323):2072-7.
Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised trial.
Chiasson JL1, Josse RG, Gomis R, Hanefeld M, Karasik A, Laakso M; STOP-NIDDM Trail Research Group.
(**)
Chiasson JL, Josse RG, Gomis R, Hanefeld M, Karasik A, Laakso M, STOP-NIDDM Trial Research Group
: Acarbose treatment and the risk of cardiovascular disease and hypertension in patients with impaired glucose tolerance: the STOP-NIDDM trial. JAMA 2003; 290: 486-494.