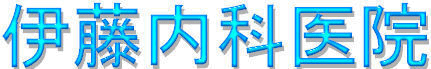飼い猫が媒介したと推定される重症熱性血小板減少症候群の1例
ヒロシマ医学 2025年3月号より
谷本 のりこら
重症熱性血小板減少症候群は、SFTSウイルスによる新興感染症であり人獣共通感染症である。症例は58歳。女性。発熱・倦怠感を主訴に救急外来を受診した。問診から、飼い猫が元気がなく、動物病院の受診によりマダニによるSFTSと診断されていたことが判明した。患者は猫の看病中に鼻汁接触、爪による擦過を認めていた。来院時の血液検査で、血小板の低下、軽度の肝障害を認め、SFTS感染症を疑い、精査加療目的に入院とした。その後好中球、血小板の著しい低下がみられ、発症5日目の骨髄穿刺では軽度の血球貪食症候群を認めた。発症6日目、PCR検査結果によりSFTSと確定診断された。本例の経過からSFTS発症動物の血液や体液を介してヒトに感染する可能性が示唆された。発熱患者に対して、熱源が不明な場合や発疹・肝腫大やリンパ節腫大などを認める場合は、SFTSを疑いペットに関する詳細な問診が必要である。本例は、発症早期に問診でSFTSを疑い、迅速な診断と治療につながった1例である。
コメント 治療はメチルプレドニゾロン500mgx3日間で改善している。
獣医師はSFTSをきちんと診断できている。よくあるのだろうか。ダニに咬まれた猫や犬から人間にうつる、という経路があるらしい。
四半世紀前のレジデントの頃、HPS(血球貪食症候群)の患者さんを何人か入院で治療させていただいた。CHOP療法で免疫抑制をしていた。
SFTSという疾患概念がその頃はなかった。
血液データではトランスアミナーゼ、LDH, フェリチンの上昇。下痢などの消化器症状もあるらしい。
下記 考察より引用
2017年4月にSFTSを発症したネコが初めて見つかり、本邦で2019年10月までに、ネコ120匹、犬7例の発症が確認されている。動物でも人と類似したような症状がみられ、致死率はネコで60-70%、犬で30%程度と報告されている。イヌよりもネコにおける発生頻度が高く、さらにネコは重症化して死に至ることが多いとされている。本例でも、飼い猫は死亡していた。近年、前述のように発症動物からの飼い主、獣医療関係者への感染も散見されており、獣医療従事者のSFTS届け出症例は、2018年から2022年7月までの期間に10例である。動物からの感染経路の例として、SFTSに感染したネコや犬といったペットによる咬傷あるいは接触により、SFTSウイルスに感染したり、一部症例では死亡した患者の報告があり、ペットからの感染リスクの可能性にも注意が必要である。唾液を含む体液中に大量のウイルスを放出するが、本例もペットである飼い猫の体液により罹患した可能性が否定できないケースであった。原因不明の発熱患者に遭遇した際に、消化器症状やリンパ節腫脹といった身体所見や、白血球や血小板の減少、トランスアミナーゼやLDH、フェリチンの上昇といった採血所見を認めた場合は、SFTSを鑑別に挙げ、患者の行動歴のみならず、ペットの有無やその健康状態の問診を行う価値がある。