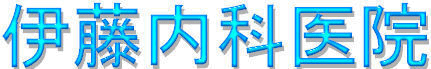湿潤療法の歴史(湿潤療法を発明したのは誰?)
夏井睦先生 新しい創傷治療より引用・・・この大発明をしたのは二人の日本人!
鳥谷部先生とラップと私
私の記憶が確かなうちに,「私の側から見た鳥谷部先生とラップ療法」について事実関係をまとめておこうと思う。私が最初に創傷被覆材で外傷治療を行ったのは1996年9月頃(秋田県の病院に勤務していた),最初にインターネットで「創傷治癒の新しい知識」について書いたのが1999年,そして「新しい創傷治療」というサイトを開設したのは2001年10月1日である(山形の病院に勤務していた)。
ちなみに,私が一番最初のインターネットサイト『超絶技巧的ピアノ編曲の世界 ー体育会系ピアニズムの系譜ー』を開設したのは1996年10月で,当時は個人のインターネットサイト自体が珍しく,ホームページ作成ソフトも市販されていなかったと記憶している(少なくとも,使い物になるソフトは市販されていなかった。このため,当時から現在にいたるまでエディタでタグを直接入力してサイトを運営している)。さらに言えば,NifftyやPC-VANが個人向けにインターネット接続サービスを始めたのは1994年である。鳥谷部先生は1996年(偶然にも私が治療を開始した時期と同じ)に宮城県の病院でふとした思いつきから「褥瘡に食品包装用ラップが使えるんじゃないか」と思いつき,褥瘡にクレラップを張ってみたらしい。また,インターネットサイト「褥瘡のラップ療法」を開設したのも2001年と,これまた偶然にも私のサイト開設と全く同じである。要するに,宮城県で鳥谷部先生が,秋田県で私が,ほぼ同時期に全く別個に全く偶然に似たような治療を始めたのだ。
私と彼は東北大学医学部の先輩・後輩関係にあるが(もちろん私が後輩ね),最初のメールのやりとりは2002年の初めの頃に始まり,直に顔を合わせたのは2002年7月の「仙台褥瘡・創傷セミナー」が最初だった。
ただ正直に言えば,私は「褥瘡のラップ療法」を知った時はさほど興味を持たなかった事は,正直に告白しよう。私の興味の対象はあくまでも外傷だったからだ。当時の私は「創傷被覆材でどのような傷が治せるのか,どのような傷は治せないのか,どのような傷には使えるのか,どのような傷には使ってはいけないのか」という問題に直面していてラップどころではなかったのだ。
なぜかというと,当時は創傷被覆材のメーカー側ですら「外傷に創傷被覆材が使える」ことを知らなかったし,外傷に創傷被覆材を使った文献は世界中でほぼ皆無だった。
そんなことも知らずに創傷被覆材を使った治療を始めてしまった私は,さまざまな問題に直ちに直面してしまい,それらの問題を解決しないことには一歩も先に進めなくなってしまったのだ。
だから,褥瘡に関わっている暇はなかったし,創傷被覆材以外の治療材料について考える余裕もなかったのである。あの当時の私の頭は創傷被覆材で一杯であり,この未知の可能性を秘めた治療材料の限界を探ることで手一杯だった。もちろん,その頃も褥瘡治療はしていたが,それは日常業務として行っているだけで,すぐに治療結果がでない褥瘡の治療はあまり面白くなかったのが事実だ。外傷治療だと翌日には治療結果が出るが,褥瘡治療はそうではなかったからだ。
ちなみに,山形の病院での褥瘡治療は「最初は創傷被覆材,その後は軟膏ガーゼ」という方針だったと思う。ラップ療法の存在は知っていたが自分でやってみようとは思わなかったからだ(鳥谷部先生,すまぬ!)。当時私は「山形創傷ケア研究会」の設立メンバーであり,創傷治療については積極的に発言していたが,褥瘡治療についてはそれほど熱心ではなかったのだ。
私が褥瘡のラップ療法を始めたのは,2003年4月に相澤病院に移ってからである。私が同院に赴任すると同時に,同院での褥瘡治療を「食品包装用ラップを使ったラップ療法」に全面的に切り替えたからだ。私が外傷治療に最初に食品包装用ラップを使った日付ははっきりしている。2003年11月10日に前腕熱傷の治療に使ったのが最初であり,2例目の使用は11月21日に肘部の皮膚損傷だった。
褥瘡にラップを使っていても外傷での使用に踏み切るのに数ヶ月かかったのはなぜかというと,各メーカーが持ってきた試供品の創傷被覆材や治療材料が豊富にあって,特にラップを使用する必要性がなかったからだ。しかし,広範囲の深い熱傷を試供品だけで治療するのは無理だったため,しょうがなくラップを使ってみた,というのが真相だったような気がする。
こんな次第で私はラップを熱傷や外傷治療に使い始めたが,鳥谷部先生のラップ療法があったからこそ,ラップ使用に踏み切れたと思っている。もしかしたら,私単独でも「ラップが治療に使えるんじゃないか?」と思い付いたかもしれないが,実際の治療での使用を決断できたかどうかは怪しいものだ。医療材料でないラップを意識ある患者の治療に使うには,並大抵でない勇気が必要だからである。褥瘡にラップを使った先駆者がいたからこそ,私もラップ使用に踏みきれたのだ。
従って,外傷(熱傷・褥瘡を含める)の治療におけるラップの使用は鳥谷部先生が先駆者であり,他の誰でもないことは私が証言する。あの当時,彼以外の誰も,褥瘡治療にラップをつかうという破天荒な発想ができた医者はいなかった。
もちろん,かなり昔から皮膚科ではODT療法としてラップを使われてきたことは周知の事実であるが,それはあくまでも湿疹などの皮膚疾患に限定した使用であり,広範な皮膚欠損,深い皮膚欠損創に対するラップ使用ではない。実際,日常的にラップを皮膚科疾患の治療に使っていた皮膚科医で,褥瘡や外傷にラップを使っていた医者はいなかったと思うし,仮にいたとしても,それを他人に伝えよう,治療として確立しようという意志は持っていなかったのは確かである。
ちなみに,ラップ療法の素材としてなぜポリエチレンがいいのかについて教えてくれたのも鳥谷部先生であり,それは彼が相澤病院にやってきた直後だと記憶している。彼は生来の化学オタクであり,私の目の前で何も見ずにポリエチレンの分子式をスラスラと書き,なぜそれが安全で無害か,燃やしてもダイオキシンなどが発生しないかを教えてくれたのだ。ちなみに私は物理学は好きだが化学はちょっと苦手であり,この時から彼に一目置くようになった。
そういえば,あの頃から鳥谷部先生は「ダイオキシンというのはタンパク質と食塩を一緒に燃やすと発生する物質で,つまり,生物の遺骸が燃えると必ず出る普遍的物質なんだよね。そういう自然の産物を最悪の発ガン物質呼ばわりで騒いでも意味が無いよ」と教えてくれたことを今でも覚えている。当時は「ダイオキシンはもっとも恐ろしい発ガン物質」というマスコミ報道一色で,それを頭から信じていた私は非常にびっくりしたことを告白する。
「化学や物理を基礎から知っていないとこういう発想は出ないな,自分も科学を基礎から勉強し直さなければ鳥谷部の足元にも近寄れない」と考えるようになり,基礎から勉強するようになったのはこの頃である。
ちなみに,当時は「恐怖のダイオキシン」報道一色であり,落ち葉焚きは危険,正月飾りを燃やす地域の風習も危険と,あれもこれも廃止された時期だが,現在,ダイオキシン報道はパッタリと姿を消している。どうやら「ダイオキシンは危険ではなく,最初のデータが間違っていた」かららしい。ちなみに,「ダイオキシンについての最初のデータは間違っていて,実は危険ではない」と報道されたことはないと思う。
この点でも鳥谷部先生は化学の知識を元に事態を正しく分析・認識していたことがわかる。以上が,私の側からみた「ラップ療法事始め」である。こんなわけで,私はこれまで自分の「ラップを使った外傷・熱傷治療」を「ラップ療法」と呼んだことはないし,今後,呼ぶつもりもない。理由は次の3点である。
「ラップ療法」という命名は鳥谷部先生のオリジナルであり,彼の名前とセットにして使われるべき語句である。
私がラップを使った治療を始めたのはかなり後になってからであり,私のオリジナルではない。
ラップ療法という名前は褥瘡治療で最初に使われた名称であり,他の治療法にラップ療法の名を冠することは許されない。
ちなみに,私の全国デビューは2001年1月の「小児ストマリハビリ学会 ランチョンセミナー」であるが,全国の医者を相手にしての全国デビューは2002年4月18日の「日本形成外科学会総会 ランチョンセミナー」の講演である。何しろ,田舎の病院の肩書きもない無名の形成外科医が形成外科学会総会で講演するのだから,ものすごいプレッシャーだったことを覚えている。
後で聞くと,同時に6会場でランチョンセミナーが開催されていたらしいが,私のランチョンセミナーの会場は超満員状態で立錐の余地もなかったことを記憶している。しかも,演壇に立つと前方の席は全国の錚々たる形成外科教授たちで埋め尽くされているのだ。それだけでもプレッシャーなのに,目の前にいたのは「学会うるさ方」として知られている福島県立医大の小野一郎教授である。これまで,学会発表のたびに小野教授の鋭い質問に立ち往生した記憶しかない私としては,胃が痛くなるような光景だった。
そして講演が終わり質疑応答に入ったが,真っ先に手を上げて質問したのがこの小野教授だった。どんな質問をしてくるんだろうと,正直,演壇から逃げたくなった。
しかし,彼の言葉は予想を超えていた。私の記憶では次のように話されたと思う。これほど感銘を受け,これほど感服した発表を聞くのは初めてかもしれません。治療成績も素晴らしければ,理論的にも非の打ち所はないと思います。
実は私も「傷は乾かしてはいけない。消毒はしなくてもいい」ということは知っていましたし,自分でもこういう治療は20年前からしています。しかし,それを他の人に伝えようとは思っていなかったし,他の医者を説得しようとも思っていませんでした。どうやったら彼らにそれを伝えられるかを,そもそも考えていなかったからです。
なるほど,こうやって治療例の経過をきちんと写真で追っていけばいいだけだったのですね。なぜ自分がこれに気がつかなかったのかと悔しいです。
これからもどんどん治療経験を重ねて教えて下さい。今回は質問はありません。
なぜこんなエピソードを引用するのか。小野教授はとても勉強熱心な人なのだが,その彼が2002年4月の時点で「創傷治癒の理論は知っていたが,それを現実の治療に応用していない。応用していたとしても限定的で発表できるものでなかった」と明言しているからだ。つまり,創傷治療のエキスパートであるはずの形成外科の教授ですら,2002年の時点ではこうだったのである。
ちなみに,このセミナーには北大の大浦教授(当時)も参加されていたと記憶するが,「いやいや,私は以前からこういう治療を知っていて,実践していますよ」というような発言をされることはなかったと明記しておこう。(2010/04/19)