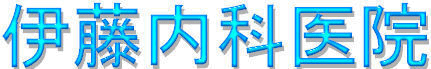日本における亜鉛欠乏性味覚障害の実態
上記より
日本における味覚障害の発症率は、欧米と比べて高いというデータがある。これまでの栄養調査のデータなどから、欧米と異なる点は以下のように考えられる。①動物性たんぱく質の摂取量が少ないため、欧米よりも日常的な亜鉛摂取量が低いと見積もられる。②精製食品(加工品)の摂取量が多い。③投薬による障害が多い。(=高齢者、中高年の年齢人口が多い)。一例として、利尿剤の炭酸脱水素酵素阻害薬(アセタゾラミドなど)治療による味覚異常の発症はひとつの例である。④若い人のコンビニ病。すなわち、ほとんど連日コンビニなどで売られているできあいの食品ばかりを食べている人での発症が増えてきた(できあいの食品は、一般に腐敗をよぶするための高食塩・高糖質含量のものが店頭に並べられるし、各種の食品添加物の使用が多いことも事実である)。富田らは、食品添加物の例として、ポリリン酸ナトリウム、EDTAナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウムなどをあげている。なお、フィチン酸(イノシトールポリリン酸)は、豆類などに含まれる天然の亜鉛キレート物質であるが、日常の摂取量程度では影響がないと判断されている。③古来の排泄物の還元によらない農法が増えてきたことと、亜鉛などを制限した化学肥料によって、土壌中あるいは植物中のミネラル類(亜鉛、鉄、銅、ヨウ素、マンガン、セレンなど)の量が減ってきたとする説がある。植物等におけるミネラル含量・ビタミン含量がすくなくなってきたデータが一部で出されているようではあるが、なお実証される必要がある。ミネラルが不足ぎみの植物を食べる家畜の肉などにおいても不十分な亜鉛含量となるのは、容易に考えられることである。