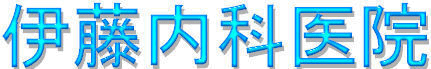99.9%が誤用の抗生物質 医者も知らないホントの話 岩田健太郎
はじめに
抗生物質は、よくも悪くもない
問題は、使われ方 どこが、どのように、なぜ間違っているのか?
抗生物質の4つのリスク・・・副作用、耐性菌、お金、不足
抗生物質のリスクを上回る利益を、本書ではお届けします
第一章 かぜに抗生物質は必要ない
かぜに抗生物質を処方していないか?
不適切使用は世界的
日本ではどれくらい処方しているか?
かぜには抗生物質が必要か?
モノとコトとの混同
かぜという現象に与える効果は、チョピットだけ・・・二次性肺炎を減らしてくれるエビデンスはほとんど皆無、1人の入院を減らすのに、なんと1万2千人以上に抗生物質の投与が必要でした。
諸外国で進む、かぜに抗生物質はNo・・・CDCのキャンペーン
第二章 21世紀の感染症の世界
近年注目の感染症 肺炎と下痢・・・ロタ、ノロでの死亡多い
19・20世紀型の感染症と21世紀型との違い
厚生労働省の勘違い
肺炎にも下痢にも「1対1対応がとれない」 21世紀型の考え方
ペニシリンが効くか、効かないかで分けていた時代
肺炎球菌といっても同じではない 実験室と体では別物・・・肺炎をおこしている肺炎球菌と、髄膜炎を起こしている肺炎球菌は「別のもの」として議論しましょうね。「どこ」の部位におきている感染症か?
現在、神戸大学病院で見つかる肺炎球菌は、全例、ペニシリンで肺炎を治せる肺炎球菌であることがわかっています。従来のPSSP,PRSPといった分類は、臨床現場では意味をなさないのです。
抗生物質の「狭さ」と「広さ」
「広さ」と「強さ」は別
急性中耳炎、急性副鼻腔炎に「抗生物質は原則必要なし」・・・このように、日本で日常的に抗生物質が処方されている病気の多くは、じつは抗生物質を必要としない病気なのです。
脾臓の大切さ 患者に何が起きているか、「コト」を判断する・・・脾臓がない人の肺炎球菌感染
CRPは測定しなくても困らない・・・アメリカなんかでは感染症の診断にCRPを全く使いません。
CRPに依存してはならないわけ
CRPは間違えやすいうえに、診断にも役立たない・・・あまりに重症すぎると上がらず
CRPの上昇、下降と抗生物質の効果は同義ではない・・・多くの感染症で、ぼくはCRPが8とか9の高濃度にあっても、抗生物質をとめてしまいます。患者が治り、細菌が死んでしまったと判断できたからです。患者さんをしっかり見ていれば、そういう判断ができるようになってきます。
CRPが下がっても、抗生物質をやめてはいけない場合もある
限りなく白に近い肺炎と、限りなく黒に近い肺炎と
グレーの度合いを見極めるのが、医者の大事な役割・・・CURB65などで判断する
第三章 「診断」という知的営為 臨床医、リッチな世界観を持つべし
かぜとかぜでない病気の境界線・・・喉頭蓋炎の多くは「インフルエンザ菌」という細菌が原因です。
かぜと急性気管支炎は分断できない
急性気管支炎と肺炎も分断できない
かぜ 気管支炎 肺炎 程度の違う「グレー」に過ぎない
リスクヘッジとしての「とりあえず抗生物質」
CT検査だって無害ではない・・・胸部レントゲン一枚の臓器放射線被ばくは0.01ミリシーベルトです。一方、成人の腹部CTでは、これが10ミリシーベルトになります。福島県の非難基準が年間20ミリシーベルトの暴露ですから、CT2回ですぐにここに達します。
CT検査大国ニッポン
日本の医療の特性を活かし、「時間」を活用する
びくびくしながら、慎重に待つ 医者の正しい態度
「微妙な状態」だから、待てる
グレーディエントを理解するー臨床医のリッチな世界観へ
臨床医学にうまくフィットする「構造主義」「構造構成主義」
「肺炎」とくくることの恣意性・・・CURB-65の条件を全然満たさない肺炎の死亡率は1%以下、すべて満たす肺炎の死亡率は50%以上でした。両者を同じに扱うわけにはいきません。
「診断」という知的営為 アウトライヤーに気づけ・・・大胆にして繊細、大雑把にして細やか 医者は矛盾する両面を併せ持つ必要があるのです。,・・・私は苦手です。でも苦手な人のほうが多いと思います。修行するしかないですね。
EBMは活用できないことも
言うことがころころ変わる指導医の真意
病気の診断はデギュスタシオン(試飲)である・・・ワインを例えに
第4章 臨床をなめんなよ 現場の医療レベルが上がらない、その理由
日本の医者は診断が苦手・・・やるべきは、「心不全」の講義ではなく、「息が苦しい」の教育なのです。
ハワイ大学医学校での驚愕(!)の体験・・・とにかくハワイ大学1年生のパフォーマンスは、それくらい圧倒的だったのです。ぼくは今まで、大学で何を教えていたんだろう、と、とても恥ずかしい思いがしました。
問題は「教え方」の差である・・・日本の医者の多くは、「自分の専門領域の病気」についての知識しかありません。
臨床医学をなめてきた日本・・・日本の医学部の教授になる要件(=基礎研究の成果)が高ければ高いほど、臨床能力の担保が難しくなる。・・・・・私の修行時代はまさにこういう価値観でした。
基礎医学と臨床医学はつながっている。が、しかし
幻想の「知性」を乗り越えて 患者の真の利益へ向かう・・・ヘーゲルが信じたヨーロッパの知性や理性など、幻想に過ぎなかった
基礎医学をそのまま臨床に応用する危険・・・たとえば、敗血症に高容量のステロイドを投与すると、かえって死亡率を高めてしまうことが知られています。(少ない量ならこの限りではない)
ARDSに対するエラスポールについても、海外ではむしろ死亡率を上げてしまう、という臨床試験の結果が出ています。
基礎から臨床への遠い遠い道のり
「ついでに臨床」は不遜な行為・・・21世紀の現在、優れた臨床医でありながら、同時に優れた基礎研究者であることはほとんど不可能です。・・・・ぼくら臨床医の目から見ると「あの人は患者さんは診ないほうがいいんじゃないの」とすら思えるほどです。
基礎医学の経験を臨床で活かせるかの分水嶺
さらに広い文脈で病気をとらえる・・・トキソプラズマ 動物からの感染
正しい医療や満足度は、ひとつのものさしでは測れない
非常にめぐまれた日本の医療へのアクセス しかし・・・まず、日本の多くは、患者さんと十分なコミュニケーションをとっていません。患者さんの話を聞かず、自分の価値観を押し付けすぎです。
医療の質を下げている、医者と患者の共犯関係・・・自分が飲んでいる薬が何なのか知らないのは、日本の患者さんだけでした。
第5章 経口三世代セファロスポリンは、99.9%が誤用
なぜ「三世代セファロスポリン」はたくさんあるのか
世界最大の三世代セフェム消費国、ニッポン
99.9%の三世代セフェムの処方は、間違いである・・・アメリカ心臓協会が出したガイドラインでは、ほとんどの歯科の診療では、予防的な抗生物質は出さないように推奨しています。また、もし用いるとしても、アモキシシリンのような、ペニシリン系抗生物質が推奨されています。
口の中の細菌はグラム陽性菌が多く、グラム陰性桿菌に強い第三世代セフェムを用いるメリットはほとんどありません。
飲んでもほとんど吸収されない抗生物質
日本のいい加減な臨床試験
「本当に効くか」が実証されないままに、薬が使用される
三世代セフェムにも副作用はある・・・昔は三世代のセフェムはそんなに危険ではない、といわれてきましたが、現在ではクリンダマイシン、そしてニューキノロン製剤とともに、三世代セフェムはディフィシル菌による腸炎(儀膜性腸炎)の最大のリスクです。
カルニチン低下による低血糖発作
正しい使い道 命にかかわる感染症に、点滴、大量投与・・・インフルエンザ菌やモラキセラに
細菌性髄膜炎(やはりインフルエンザ菌、ペニシリンが移行しにくい肺炎球菌性髄膜炎にも)
インフルエンザ菌が多い急性喉頭蓋炎に
切り札が使えなかった 感染症の子供を亡くした経験
経口カルバペネムなんてもってのほか いい加減に、目を覚まそう・・・切り札をどうでもいい時に使ってどうする!!
マクロライドも誤用が多い 心臓に副作用も・・・不整脈や心電図異常をおこすことがある
問題は副作用があることではなく、必要のない人が使用すること
薬剤耐性菌の問題・・・カルバペネム耐性緑膿菌は、日本ではもう珍しくない。
カルバペネム耐性のアシネトバクターもちらちら日本でみつかるように。
クレブシエラ、シトロバクターなど、お腹の中にいる腸内細菌と呼ばれる細菌群でも、カルバペネム耐性菌は見つかるようになっています。
腸内細菌まで耐性菌に
新しい抗生物質が、よいわけではない・・・治療の効果が小さく、かつ危険な薬が一番売れている。いったい日本の医者は何を勉強しているのでしょうか。
ぼくが古い抗生物質を使う理由
第六章 日本感染症界の「黒歴史」
日本の感染症対策は、優れていた。
数々の感染症が、姿を消した。
「死に至る病」からの救いの薬 抗生物質の登場
抗生物質使用の黒歴史 救いの薬からとりあえずだしとけ
抗生物質とマーケット
開発能力は高い、でも臨床応用はヘタ
効かなくてもよいから副作用だけはおこすな 的発想・・・十分量投与しない
耐性菌の増加と、抗生物質誤用の歴史・・・マイコプラズマはマクロライド耐性になってしまった。
テトラサイクリン(ミノマイシン等) のような歯に色素沈着をおこす薬を使わなくてはいけない状況。
少量長期投与の功罪
日本の大腸菌は「キノロンだけ耐性」・・・日本では尿路感染といえばキノロンというパターン認識、ナントカのひとつおぼえな処方がとても多いのです。
クラビットに感受性がある大腸菌は63.7%しかなかったというデータがある。
神戸大学ではST合剤や点滴の三世代セフェムを第一選択に推奨している。
泌尿器科は、感染症に強くない
感染症は医者になめられている
抗生物質、冬の時代へ
抗生物質を救うために
「右肩上がり」の考え方に決別を、そして、もっと危機感を
第七章 もっと感染症のプロを 日本の感染症専門医、その信頼性について
横断的領域がやっつけ仕事になる理由
やっつけ仕事から感染症内科へおまかせへ
もはやそれなしの時代は戻れなくなる、はず
感染症のプロと呼べる人がいない
足りなすぎる感染症専門医
専門医の問題、指導医の問題
年寄りを優遇する日本の制度
厳しいアメリカの研修制度
専門医資格が簡単にとれてしまう日本
本当の専門家を育てるために
最終章 さらば、足し算の医療 ポリファーマシー(多薬剤処方)の問題
ポリファーマシーはなぜ起きるのか?・・・8剤以下に
身近な薬にも、危険はひそんでいる
足し算の医療は、本当に患者のためになっているのか